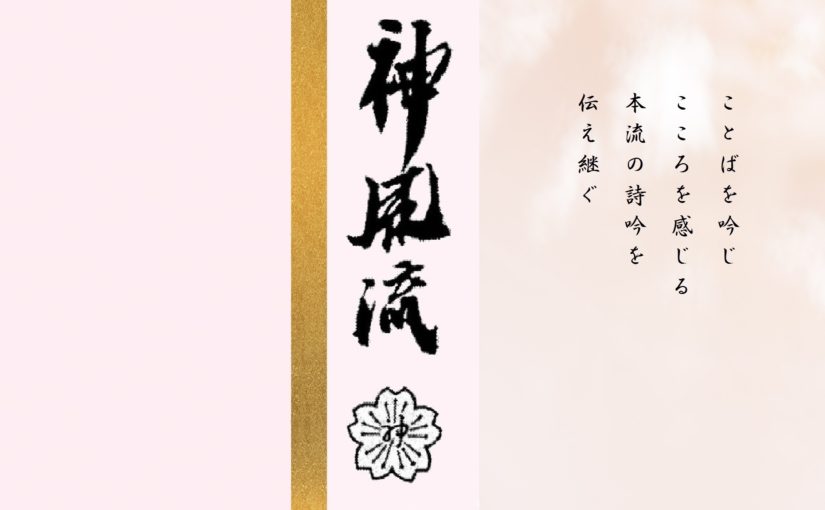日本には、古くから詩歌の「ことば」を声に出して「詠む」文化がありました。
「志の之くところ、言を永くするなり」
こころが動かされたとき、人は声を長くひいて表現します。それが響きとなり、旋律となり、詩吟の節(節調)が生まれました。
詩吟とは、その詩文(漢詩や和歌)に日本古来の節を付けたものです。
詩吟は、花や月、風、雲など自然の風物にことよせて、人生の喜怒哀楽を吟じるものです。長い歴史の中で、人生観・自然観が謳われ発展してきました。
江戸時代には、武士のあいだで、漢詩の素読とともに自己の精神修養として広がりをみせました。特に幕末の志士たちにとって、心の表現と詩吟の真髄とは合致するものでした。
気概、勇壮さ。よろこびや感動。愛しみや哀しみ。
先人たちの心に依拠し、力強い気魄のある節調もあれば、想いが溢れるほどの情緒的な節調もあるのが神風流の詩吟の魅力です。
神風流は日本で最も歴史ある流派ですが、和歌の美しさ、漢詩の奥深さを味わいつつ、数多の優れた吟譜を生み出し、節調を磨いてまいりました。神風流の詩吟の特徴は、決して単調ではない、多彩な節調にあります。また、「琵琶行」や「長恨歌」などの長詩といった符付けにも定評があります。これらは、一朝一夕に出来上がったものではなく、長い間に積み上げてきた精華によるものです。日本の伝統的秘曲とも言える神風流の詩吟を後世に伝えて参りたいと思います。
自ら声を出し、心を感じることの素晴らしさ。神風流を通して、詩吟の魅力を多くの方に知っていただけましたなら幸いです。
詩吟神風流三代目総元 岩淵神風